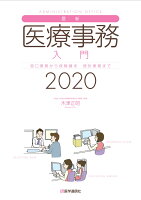2018年度の診療報酬改定で新設された「重症度、医療・看護必要度Ⅱ」。
内容が複雑な重症度、医療看護必要度にⅡという制度が追加されて、重症度、医療看護必要度について詳しくない方は混乱されているのではないでしょうか?
また、ⅠからⅡに切り替えを考えているけれど、手続きがよくわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そんな重症度、医療・看護必要度について、こちらの内容を紹介していきます。
- 重症度、医療・看護必要度とは?
- 重症度、医療・看護必要度ⅠとⅡの違いは?
- 重症度、医療・看護必要度ⅠとⅡの切り替える方法でのポイントは?
※この記事は2020年診療報酬改定をもとに作成しています。
目次
1.重症度、医療・看護必要度とは?
まずは重症度、医療・看護必要度Ⅱの紹介に合わせて、重症度、医療・看護必要度とはなにかから紹介していきます。
また、なぜこの指標が重要視されているのかについても触れていきます。
1.1 重症度、医療・看護必要度とはなにか?
重症度、医療・看護必要度は2008年度の診療報酬改定で急性期の患者等の手厚い看護の必要性を測定するための指標として導入されたのがはじまりです。
当時は重症度・看護必要度と呼ばれ、2014年度の改定で今の重症度、医療・看護必要度という名称に変更になりました。
看護の必要性を測定ということで、簡単に言えばどの程度看護を提供しているか、また看護のかかり具合がこの病院ではどの程度あるのかを測定するのがこの指標です。
1.2 重症度、医療看護必要度ⅠとⅡ
2018年度の診療報酬改定で重症度、医療・看護必要度はⅠとⅡの二つに分けられました。
これまでの看護職員が直接評価していた重症度、医療・看護必要度はⅠになっています。
そこに評価の業務量削減やより正確なデータを取得するために、診療実績データから評価を行う重症度、医療・看護必要度Ⅱが新設されました。
重症度、医療・看護必要度Ⅱでは評価項目であるA・C項目をDPCデータを用いて評価を行います。
1.3 重症度、医療看護必要度の重要性
この重症度、医療・看護必要度がなぜよく話題に上がるのか? 大きな理由としては入院料の算定に要件として必要になってくることが挙げられます。
例えば急性期一般入院料では算定の基準の中に重症度、医療・看護必要度の評価で評価基準を何%以上を満たす患者がいることというのが条件になっています。
急性期医療を提供していて、多くの難しい治療を行っている場合はそれだけ看護の提供量は大きくなります。
そういった病院は高い入院料が算定できるといった仕組みになっています。
もちろんこの重症度、医療・看護必要度だけで入院料が決まるわけではありませんが、基準の一つとして設けられているため、多くの医療機関ではこの重症度、医療・看護必要度は重要視されています。
また、現状の日本の医療や患者の状態像などの分析にも集めたデータは分析にもよく使用されます。
診療報酬改定前ではこの重症度、医療・看護必要度のデータをもとに分析され、改定の内容を決めている項目もあるので、分析の分野でかなり重要度が高い項目になっています。
この重症度、医療・看護必要度についてもっと詳しく知りたい方はこちら記事もあわせてご覧ください。
https://medical-information-room.com/barometer_barometer_nursing/
参考文献
■平成30年度診療報酬改定
2.重症度、医療・看護必要度Ⅱのおさえておきたいポイント
1章では重症度、医療・看護必要度を中心に紹介しました。
この章では重症度、医療・看護必要度Ⅱにおさえておきたいポイントとして
- 重症度、医療・看護必要度Ⅱの評価方法
- 重症度、医療・看護必要度ⅠとⅡの評価基準
- 重症度、医療・看護必要度の切替のポイント
について紹介していきます。
2.1 重症度、医療・看護必要度Ⅱの評価方法
重症度、医療・看護必要度Ⅱは診療実績データから評価を行います。
具体的にはA項目とC項目について、DPC調査のEFファイルから該当の有無を評価します。
EFファイルに記載されているレセ電算コードに対して、厚労省が出しているコード一覧に照らし合わせて該当しているかを判断します。
下記の資料の「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」に各評価項目とレセ電算コードの関係が掲載されています。
厚生労働省:基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
例えば4/1に酸素吸入(レセ電算コード:140005610 )を行った場合は4/1の呼吸ケアは有りになります。
このような評価をA項目とC項目で行い、B項目に関しては従来通りの看護師の評価を行います。
2.2 重症度、医療・看護必要度ⅠとⅡの基準
入院料の算定に重症度、医療看護必要度の評価が必要で、基準が設けられているものがあります。
この基準はⅠとⅡで違いがあり、2020年度の診療報酬改定では下記の値が設定されています。

ⅠよりⅡの値が低く設定されていることがわかると思います。
これは事前の調査でⅠの評価よりⅡでの評価のほうが低い傾向にあることが示されたため、このような評価基準になっています。
2018年度の改定時にはⅠとⅡに大きな差がありましたが、2020年度の改定でその差が縮まっています。
2.3 重症度、医療・看護必要度の切替のポイント
ここまで重症度、医療・看護必要度Ⅱについて紹介してきました。
EFファイルから評価できることから重症度、医療・看護必要度Ⅱに切り替えたいと感じる方は多いのではないでしょうか?
重症度、医療・看護必要度Ⅱに切り替えるにも施設基準が設定されているので切替のポイント見ていきたいと思います。
いくつか基準がありますが、重要なのは下記になります。
Ⅱを用いる場合は、届出前3月において、重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者の割合について、ⅠとⅡの各入院料等の基準を満たした上で、Ⅱの基準を満たす患者の割合からⅠの基準を満たす患者の割合を差し引いた値が0.04を超えないこと。- 評価方法のみの変更を行う場合は、その切り替えは4月又は10月であり、切り替え
る月の10日までに変更の届出を行うこと
切替月は4月、10月になり、それぞれ4月10日、10月10日までに届け出を行う必要があります。
このとき4月1日に届け出を行う場合の過去3月分は1月~3月のデータから評価を行います。
もし3月に届け出を出す場合は12月~2月のデータで評価となります。
切替月と届け出の締め切り日が明確に定められているので、切替を検討している医療機関は日付を間違えず届け出を行いたいところです。
2018年度改定時には切り替える際にⅠとⅡの評価基準の差が要件にありましたが、2020年度からその要件は削除されています。
参考文献
■令和2年度診療報酬改定
■平成30年度診療報酬改定
■告示3 基本診療料の施設基準等
保医発0305第2号 基本診療料の施設基準等及びその届け出に関する手続きの取り扱いについて
■診療点数早見表 2020年4月版
まとめ:重症度、医療・看護必要度Ⅱのポイント
重要度、医療・看護必要度Ⅱとは?からⅡのおさえておきたいポイントについて紹介してきました。
働き方改革が推進されている社会で、少しでも業務削減につながる可能性があるので、重症度、医療・看護必要度Ⅱの導入を検討してはいかがでしょうか。
新設されて間もない制度ですので、今後の動向にも注意していきたい項目です。
それでは最後に今回の記事のまとめです。
- 重症度、医療・看護必要度Ⅱは診療実績データから評価を行う
- A項目・C項目はEFデータから評価、B項目は従来の看護師の評価
- 入院料の算定基準でⅠの評価基準とⅡの評価基準は異なる